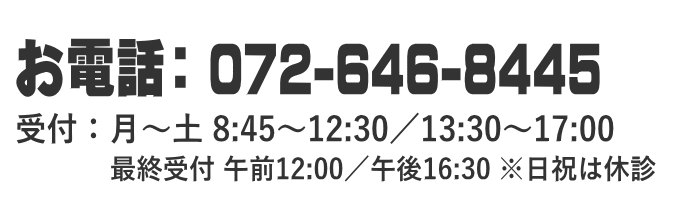梅雨が明け本格的な夏を迎えた京都の街では、あの有名な7月17日の山鉾巡航以外にも祇園祭のさまざまな行事が執り行われる。千年超の歴史を誇る祇園祭は、貞観11年(869年)の巨大地震で起こった大津波による東北沿岸の被害など、容赦なく続いた災厄を祓い清めるために始まったものだ。中世の古より連綿と続く古都の一大イベント。しかし今年の祇園は事情が異なる。奇しくも3月11日、同じ東北地方を襲った未曾有の大災害による犠牲者を弔うとともに、生還した被災者の現状を慮る京都市民の心情が込められた特別な祭なのである。
そんな背景の中で7月9日と10日の両日、京の街の喧騒を離れた東山・岡崎の地で第2回日本口臭学会学術大会が開催された。会場である京都市国際交流会館には、口臭の診療に携わる歯科医師を中心に大学の基礎研究者や耳鼻咽喉科の医師、薬学者、企業の研究者など、この学会ならではの多彩な顔ぶれが集まった。特に今回は久保伸夫先生(大阪歯科大学耳鼻咽喉科)が大会長を務められたこともあり、耳鼻咽喉科医の姿が目立つ大会となった。
今年度のテーマは「口臭を科学する」、これに沿った特別講演やシンポジウムが相次いで催された。初日である7月9日には三輪高喜教授(金沢医科大学耳鼻咽喉科)による「嗅覚の生理と嗅覚障害の病理」に関する特別講演が行われ、嗅覚障害において口臭症は「悪臭症」と「自己臭症」に分類されるとのお話を拝聴した。一般演題も含め、発表ごとに繰り広げられた活発な質疑応答が、口臭という謎多き問題の解明に挑む参加者の熱意を雄弁に物語っているようであった。また、例年通り韓国からは多数の研究者が参加したが、英語で4題発表した後の質疑応答では英語と韓国語、日本語が飛び交う印象的な場面が展開した。その後、会場近くのシェラトン都ホテルに場所を移して行われたレセプション・パーティーでは会員の活発な交流が持たれた他、京都らしく芸子さんによる舞も披露された。
翌7月10日にはシンポジウムが開かれた。パネリストは松田秀秋教授(近畿大学薬学部)、久保伸男準教授、永井哲夫先生(慶応大学歯科口腔外科)の面々で、それぞれの立場から口臭を科学的に分析された。松田先生は口臭を東洋医学的見地から捉え、漢方処方の歴史的考察について薬学者の立場から発表された。次に、久保先生が第3者には感知できない、患者のみが感じる口臭を「感覚障害」と捉えて発表され、永井先生は自己臭症について心身医学的な観点から発表された。
他に、韓国のBaek先生(亜洲大学先進歯科学)を招いての講演では韓国における口臭治療と研究の歴史、そして主要文献が報告された。横井基夫教授(名古屋市立大学口腔外科)の特別講演は、「舌診」により舌の色調や形態の変化を細かく観察することが、診断や治療に結びつくということを主題としていた。すなわち五臓の不調から口臭が生じること、「胃熱」「腎虚」などの東洋医学的な病因診断が口臭治療において有効であることなどが強調された。この学会の前身である口鼻臭臨床研究会からの課題であった「口臭治療ガイドライン」の策定は佳境に入っており、来年には最終案が示されると総会で報告があった。
また、学会と併催された市民公開講座も充実した内容であった。前田伸子教授(鶴見大学口腔微生物学講座)は口の中に生息する細菌が口臭の原因物質を産生すること、そしてこれら細菌の繁殖を抑制することこそが口臭予防につながることを、わかりやすい言葉で解説された。さらに本田俊一先生(医療法人ほんだ歯科)は、口臭は誰にでも起こりうる問題であることや口臭が起こりやすい状況などについて解説された。中でも唾液の大切さや正しい歯みがきのタイミングについて話が及ぶと、参加した市民聴講者たちがより一層熱心に聴き入る姿が印象的であった。その様子からは、私たち研究者のみならず社会全体の口臭に対する関心の高さがうかがえ、本大会が開催された意義を改めて確信させてくれた。
大会終了後帰路につくと、四条大橋近くで馬に乗るお稚児さんや浴衣を着た若者の行列に出くわした。「お迎提灯」という祇園祭の一行事で、夜になると四条大橋の上で3基の神輿が清められるという。今なお予期せぬ苦難にあえぐ彼の地の人々に、祇園の鎮魂歌は届くだろうか。
(樋口均也 記)